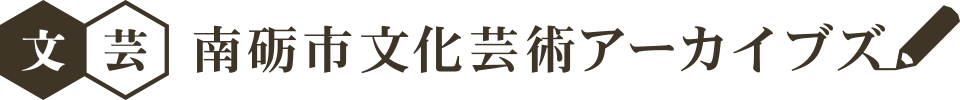

- 文字サイズ
- 小
- 中
- 大
南砺市に存在している数多くの文化芸術資源に関する情報の一元化がこのページの目的です。 旧8町村の町史・村史等から文化芸術に関する情報をピックアップし、このページに集約しています。こちらのページは、市民の皆様の文化的知識を集約し、反映することも目的としているため、皆様から情報収集を行いながら少しずつ作り上げていくコンテンツです。
Nanto City is working to create a unified collection of information about the many cultural and artistic resources the city possesses. This section of the website will serve as a place to collect and feature information about the culture and art of the eight former towns and villages that now make up Nanto City. Content will gradually be added over time, as we collect more and more cultural knowledge from the people of Nanto City.
本页的目的在于实现南砺市众多文化艺术资源相关信息的一元化。本页汇集了原8个町村的町史、村史以及文化艺术相关的信息。本页以汇集、反映市民大众的文化知识为目的,因此内容是一边向大家征集信息一边逐步制作的。
本頁的宗旨為統整南礪市裡數量眾多的文化藝術資產相關資訊。我們從舊八町村的町史及村史中揀選出與文化藝術相關的資訊,並彙整於本頁。本頁的另一目標為集結、反映市民的文化知識,故內容將因各位提供的資訊而逐漸完善。
文化・世界遺産課にて随時更新作業を行うことに加えて、当ページの「編集フォーム」より、閲覧者の方どなたでも自由に書込・編集していただけます。
未掲載の記事を新規作成する場合は、「投稿フォーム」より書込をお願いいたします。
既存の記事の内容に修正・追加がある場合は、該当記事下部の「修正フォーム」よりご連絡をお願いいたします。
なお、編集されたものは一度管理者の方で確認しますので、反映にはある程度時間を要します。
※本ページは、JSPS科研費JP16K14997の助成を受けた成果物に基づき作成しております。
13件中 1〜10件を表示
石仏を総称してゾーサマというように、地蔵は、もっとも普遍的な石仏である。地蔵は、釈迦の入滅後56億8000万年後に弥勒菩薩が出現するまでの間、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)の輪廻に苦...
赤祖父川左岸に、祀られている。だれが、何のために造立したかは不明。赤祖父川のほとりに立つ水天であるから、おそらく水害のないことを祈ったものであろう。ここは八幡社のあったところで、「八幡のゾーサマ...
経典の講究する集会を講会と称し、転じて寺院で修する法会をさし、さらに宗教的集団組織を意味するようになり、その集会を講、御講という。五箇山十日講はその名称より、十日を集会日とした五箇山全域の講であ...
浄土真宗における講の一つで、家レベルで行うもの。各家、年1回集まる。冬ごもりの準備も一段落する11月中頃から12月にかけて、家ごとに営まれる。親類縁者を呼び、道場のボンサマ(お坊さん)に来てもら...
浄土真宗における講は、信仰面においても組織面においても中心をなすものである。五箇山は浄土真宗一色であるので、社会生活の中で講行事の果たす役割は大きい。講には、集まる範囲によっていくつかの段階があ...
八乙女山地から山麓に吹き下りる南の風で、井波地域を中心に強く吹く風。井波地域から旧庄川町の一帯は、南風の特に強い地帯である。昔から井波の一帯に強風が吹くのは、井波地域の背後の八乙女山の尾根づたい...
福光は加賀国境の霊峰医王山下に位置しているので、古くから山岳信仰を伝えてきたと考えられる。文明十三年(1481)福光城主石黒光義が瑞泉寺一揆に敗れたとき、医王山の寺坊も焼き払われてしまい、長らく...
町端・村はずれ・四つ辻・岐れ道など、町内あちこちに地蔵様を祀ったお堂が多い。地蔵信仰は中世以来の民俗で、今日に至ってもなお民間にひろく持続されている。地蔵信仰の起源は平安時代末期にさかのぼり、さ...
蛇喰の共有林を「宮さま山」と呼び、そこにはニ体の石仏が石祠に納まっている。そのうちの一体が「山の風神様」と呼ばれているもので風神の姿をしている。
天部の風天で、インドの風の神ヴァーユ...
真言密教が栄えたころ(弘法大師以後)、大門山、見越山、奈良ヶ嶽、大笠山、笈ヶ岳の峰伝いが、信仰の山、白山への修験道として、多くの行者が往来した、といわれている。さらに明治の末ごろ、大笠山の頂上か...
13件中 1〜10件を表示
この記事は市民の方からいただいた情報を元に掲載しています。
万が一、記事に間違いなどがございましたら該当記事下部の「修正フォーム」よりご連絡ください。
また、掲載されていない情報の投稿もお待ちしております。
南砺市民全員でこのNANTO Wiki を盛り上げていきましょう!