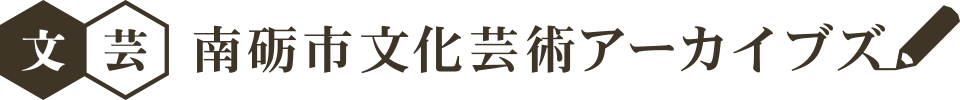

- 文字サイズ
- 小
- 中
- 大
南砺市に存在している数多くの文化芸術資源に関する情報の一元化がこのページの目的です。 旧8町村の町史・村史等から文化芸術に関する情報をピックアップし、このページに集約しています。こちらのページは、市民の皆様の文化的知識を集約し、反映することも目的としているため、皆様から情報収集を行いながら少しずつ作り上げていくコンテンツです。
Nanto City is working to create a unified collection of information about the many cultural and artistic resources the city possesses. This section of the website will serve as a place to collect and feature information about the culture and art of the eight former towns and villages that now make up Nanto City. Content will gradually be added over time, as we collect more and more cultural knowledge from the people of Nanto City.
本页的目的在于实现南砺市众多文化艺术资源相关信息的一元化。本页汇集了原8个町村的町史、村史以及文化艺术相关的信息。本页以汇集、反映市民大众的文化知识为目的,因此内容是一边向大家征集信息一边逐步制作的。
本頁的宗旨為統整南礪市裡數量眾多的文化藝術資產相關資訊。我們從舊八町村的町史及村史中揀選出與文化藝術相關的資訊,並彙整於本頁。本頁的另一目標為集結、反映市民的文化知識,故內容將因各位提供的資訊而逐漸完善。
文化・世界遺産課にて随時更新作業を行うことに加えて、当ページの「編集フォーム」より、閲覧者の方どなたでも自由に書込・編集していただけます。
未掲載の記事を新規作成する場合は、「投稿フォーム」より書込をお願いいたします。
既存の記事の内容に修正・追加がある場合は、該当記事下部の「修正フォーム」よりご連絡をお願いいたします。
なお、編集されたものは一度管理者の方で確認しますので、反映にはある程度時間を要します。
※本ページは、JSPS科研費JP16K14997の助成を受けた成果物に基づき作成しております。
63件中 41〜50件を表示
城端漆器は、城端蒔絵として広く知られている。現在、城端蒔絵として世に伝わるものを見ると、大体二つの様式に分けることができるといわれている。一つは密陀蒔絵のもので、他は白漆蒔絵である。密陀蒔絵は、...
城端曳山の屋台囃に関連するもの。三味線・太鼓・笛を伴奏する。この特殊な音楽は、曳山祭の始まった享保年間から行われ、代々指導者的芸達者がいたが、名が残る者はいない。明治に入り、最も傑出したのは荒木...
音楽家。明治二十四年三月十六日、城端町に生まれる。幼いときより音楽を好み、その才能は早くから認められていた。東京音楽学校に入り、本科器楽部を卒業、バイオリン専攻で身を立てた。県下の音楽教育の指導...
城端神明宮の春季祭礼。5月4日(かつては5月14日)が宵祭、5月5日(かつては5月15日)が本祭。宵祭では、城端神明宮から御旅所に神明・八幡・春日の3基の神輿が移され、各町の曳山と庵屋台は各町の...
城端曳山祭の特色の一つ。各町趣向を凝らしたものを1基ずつ持っている。曳山より先の時代のもので、神様を天上より御招きする古い行事の名残りである。大体の形は大きな絵番傘に約一尺巾のちりめんの幕を傘の...
屋台の中に入る囃方は若連中で、何れも家業についている男子であるとされる。その服装は、昔は東上が錦の着物に天鷲絨の帯をしめ、西上のものは赤の縮緬の着物に素袍を着ていた。これは慶応年間に全部、羽織袴...
この盆踊り歌は、古来、砺波地方および婦負郡の一部に歌われてきたもので、「西山家弥栄音頭」または「千音加礼節」ともいい、この歌は割り竹を使用して拍子をとるので「四つ折り節」ともいわれている。
むかし高瀬の神が遠く高麗の国から渡来され、この水で足袋を洗われたことから「タビ川」と名づけたという。絹や木綿の足袋にコハゼをつけたのは明治以後のことで、もとはイノシシやシカの皮で毛を外側にひもで...
福野地域安居地区にある寺。真言宗安居寺は、越中で最も古い勅願所であるという。開基は天平元年(729)、行基菩薩の草創で、聖武天皇の勅願があったといわれる。本尊は聖観世音菩薩。この本尊は、インドの...
川上中は、藩政の頃は中村といわれ、寛文10年の藩から下付された村御印には井口中村と書かれている。
しかし、明治12年に同じ砺波郡内に中村が4か村もあったため、川上中村に改称した。その...
63件中 41〜50件を表示
この記事は市民の方からいただいた情報を元に掲載しています。
万が一、記事に間違いなどがございましたら該当記事下部の「修正フォーム」よりご連絡ください。
また、掲載されていない情報の投稿もお待ちしております。
南砺市民全員でこのNANTO Wiki を盛り上げていきましょう!