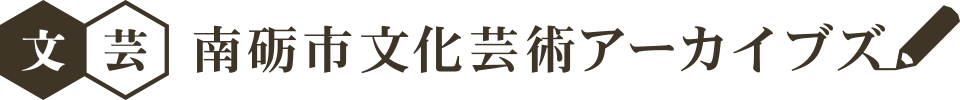

- 文字サイズ
- 小
- 中
- 大
南砺市に存在している数多くの文化芸術資源に関する情報の一元化がこのページの目的です。 旧8町村の町史・村史等から文化芸術に関する情報をピックアップし、このページに集約しています。こちらのページは、市民の皆様の文化的知識を集約し、反映することも目的としているため、皆様から情報収集を行いながら少しずつ作り上げていくコンテンツです。
Nanto City is working to create a unified collection of information about the many cultural and artistic resources the city possesses. This section of the website will serve as a place to collect and feature information about the culture and art of the eight former towns and villages that now make up Nanto City. Content will gradually be added over time, as we collect more and more cultural knowledge from the people of Nanto City.
本页的目的在于实现南砺市众多文化艺术资源相关信息的一元化。本页汇集了原8个町村的町史、村史以及文化艺术相关的信息。本页以汇集、反映市民大众的文化知识为目的,因此内容是一边向大家征集信息一边逐步制作的。
本頁的宗旨為統整南礪市裡數量眾多的文化藝術資產相關資訊。我們從舊八町村的町史及村史中揀選出與文化藝術相關的資訊,並彙整於本頁。本頁的另一目標為集結、反映市民的文化知識,故內容將因各位提供的資訊而逐漸完善。
文化・世界遺産課にて随時更新作業を行うことに加えて、当ページの「編集フォーム」より、閲覧者の方どなたでも自由に書込・編集していただけます。
未掲載の記事を新規作成する場合は、「投稿フォーム」より書込をお願いいたします。
既存の記事の内容に修正・追加がある場合は、該当記事下部の「修正フォーム」よりご連絡をお願いいたします。
なお、編集されたものは一度管理者の方で確認しますので、反映にはある程度時間を要します。
※本ページは、JSPS科研費JP16K14997の助成を受けた成果物に基づき作成しております。
58件中 41〜50件を表示
五ヶ山の文字が、文献にはじめて見られるのは、現在のところ上平村細島生田長範氏蔵の方便法身尊像の裏書きで、
大谷本願寺釈実如(花押)
永正十五年戊寅五月□□日
...
寛永7年(1667)に加賀藩の罪人(金沢藩士)が祖山へ流されたのが始まり。元禄3年(1690)から五箇山は藩の流刑地となった。加賀藩の流刑地は庄川の右岸の集落に限られていた(猪谷、田向、大島、大...
役行者(エンノギョウジャ)は、今から約1400年前の人であったが、心の狭いひとたちの申出によって天皇に捕えられ、伊豆の大島へ流された。この時、天皇からさしむけられた軍勢が、空を飛び雨を降らせる行...
道場は、形式的には本寺の布教所とされているが、道場を運営面でも経済面でも支えていたのはムラ共同体であった。求道者を中心に道場が村々に作られ、それが次第に寺院化していくのが常だが、五箇山では長く道...
五箇山の豆腐は固いのが特徴。わらで十文字に縛って、持って歩けるぐらい固い。平生は作らず、正月や祭り、報恩講、祝い事など、特別な日にだけ作られた、ハレ(晴れ)の食物である。各家で作っていた。
平地域上梨地区にある神社。昭和33年5月14日、国指定重要文化財に指定された。
白山宮の本殿は中世の歴史を示す建造物で、文亀二年(1502)の再建棟札を現存する。屋根は切妻造りに庇を...
甘稗。稗の一種。炊いて食べた。主に山畑に直蒔する。苗床で育てて移植することもある。
南瓜のこと。 ボブラだけを煮て夏の昼食の足しにした。五箇山の名産として手次寺や神主への贈り物とした。一般的に丸い南瓜のことをボブラと言い、しわのよったものはキクボブラという。村内でもボボラ・ボブ...
「りょうぶ」のこと。五月末から六月初めにかけて若芽や若葉を摘む。茹でてむしろに広げて干し、揉んでさらにツツで叩いて細かくする。茹でたものを絞り箱で絞って包丁で刻んで干すこともあった。これをクグツ...
五ヶ山は畑作地帯であり、水田が無かったから、米を主食にすることが無かった。平野部の水田地帯でも百姓家庭では混食し、団子で補うのが普通であった。五ヶ山の村々の家庭では稗・粟・またびえ・麦・豆類・大...
58件中 41〜50件を表示
この記事は市民の方からいただいた情報を元に掲載しています。
万が一、記事に間違いなどがございましたら該当記事下部の「修正フォーム」よりご連絡ください。
また、掲載されていない情報の投稿もお待ちしております。
南砺市民全員でこのNANTO Wiki を盛り上げていきましょう!