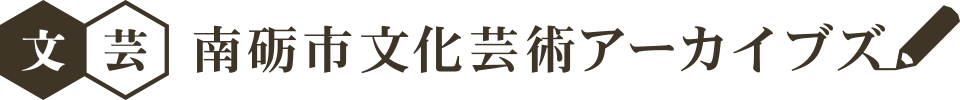

- 文字サイズ
- 小
- 中
- 大
南砺市に存在している数多くの文化芸術資源に関する情報の一元化がこのページの目的です。 旧8町村の町史・村史等から文化芸術に関する情報をピックアップし、このページに集約しています。こちらのページは、市民の皆様の文化的知識を集約し、反映することも目的としているため、皆様から情報収集を行いながら少しずつ作り上げていくコンテンツです。
Nanto City is working to create a unified collection of information about the many cultural and artistic resources the city possesses. This section of the website will serve as a place to collect and feature information about the culture and art of the eight former towns and villages that now make up Nanto City. Content will gradually be added over time, as we collect more and more cultural knowledge from the people of Nanto City.
本页的目的在于实现南砺市众多文化艺术资源相关信息的一元化。本页汇集了原8个町村的町史、村史以及文化艺术相关的信息。本页以汇集、反映市民大众的文化知识为目的,因此内容是一边向大家征集信息一边逐步制作的。
本頁的宗旨為統整南礪市裡數量眾多的文化藝術資產相關資訊。我們從舊八町村的町史及村史中揀選出與文化藝術相關的資訊,並彙整於本頁。本頁的另一目標為集結、反映市民的文化知識,故內容將因各位提供的資訊而逐漸完善。
文化・世界遺産課にて随時更新作業を行うことに加えて、当ページの「編集フォーム」より、閲覧者の方どなたでも自由に書込・編集していただけます。
未掲載の記事を新規作成する場合は、「投稿フォーム」より書込をお願いいたします。
既存の記事の内容に修正・追加がある場合は、該当記事下部の「修正フォーム」よりご連絡をお願いいたします。
なお、編集されたものは一度管理者の方で確認しますので、反映にはある程度時間を要します。
※本ページは、JSPS科研費JP16K14997の助成を受けた成果物に基づき作成しております。
48件中 11〜20件を表示
城端曳山祭にて登場する、出丸町の曳山。”布袋像”を安置している。曳山の原作は享保5年(1720)で、高砂山と称され”尉と姥”を安置していたが、宝暦12年(1762)布袋山に改められ、さらに唐子山...
城端曳山祭にて登場する、東下町の曳山。福寿山とも呼ばれている。”大黒天像”を安置している。曳山の原作は享保年間で、その後の修繕・増補によって形態・構造が拡充された。
構造は輻車(やぐ...
城端曳山祭にて登場する、西上町の曳山。”恵比寿像”を安置している。原作は享保の初め頃で、安永年間に7代目小原治五右衛門林好が作りかえた。その後、嘉永元年(1848)に9代目・10代目治五右衛門が...
城端曳山祭にて登場する、大工町の曳山。”関羽と周倉像”を安置している。享保年間に作られた原作は、明治33年(1898)の大火で焼失したため、明治39年に復元、再造された。
構造は輻車...
城端曳山祭にて登場する、東上町の曳山。”寿老像”を安置している。享保年間に作られた曳山は、安永年間に7代目小原治五右衛門林好によって改作され、その後も代々の手が加えられた。明治40年(1907)...
城端曳山祭にて登場する、西下町の曳山。”堯王像”を安置している。原作は享保年間で年代を経て随時修繕・補修され、明治・大正の改修により構造・形態が拡大、今日の曳山が形成された。
構造は...
城端の大寺。浄土真宗東本願寺派(大谷派)別格別院。本尊は阿弥陀仏。城端町の発展に深い関連を持っており、城端の中核をなす寺院である。
文明三年(1471年)、本願寺八代連如(れんにょ...
城端地域北野地区にある寺。浄土真宗大谷派。本尊は阿弥陀如来。開基了道は、もと越前細呂木出身の武士で、たまたま石山合戦(1570~80)に本願寺側の軍卒として参加していたが、本願寺法主の法縁により...
城端地域北野地区にある寺。浄土真宗大谷派。本尊は阿弥陀如来。開基は宗無といい、次郎丸と井口村川上中村の境界にある桂山より、天正五年(1577)現在地に移転した。最初は天台宗とも真言宗との説もある...
城端地域大鋸屋地区にある寺。浄土真宗大谷派。昔大鋸屋に在り、廃寺となっていたものを昭和十四年に再興した。この寺の前身は石動道林寺の大鋸屋教場で、篤信の一世義孝があずかり、月忌参りを行っていたとい...
48件中 11〜20件を表示
この記事は市民の方からいただいた情報を元に掲載しています。
万が一、記事に間違いなどがございましたら該当記事下部の「修正フォーム」よりご連絡ください。
また、掲載されていない情報の投稿もお待ちしております。
南砺市民全員でこのNANTO Wiki を盛り上げていきましょう!