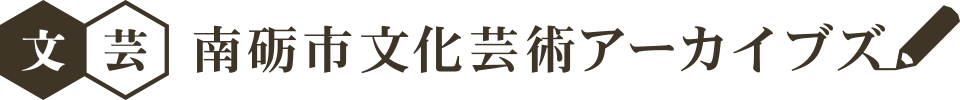福光城址栖霞園
- 福光
- 市指定
- 史跡





概要
| 名称 | 福光城址栖霞園 ふくみつじょうしせいかえん |
|---|---|
| 地域 | 福光 |
| 指定 | 市指定文化財 |
| 種類 | 記念物 史跡 |
| 所在地 | 南砺市福光(荒町)4948 |
| 指定年月日 | 昭和34年11月5日 |
| 所有者 | 南砺市 |
解説
中世、この一帯は「石黒荘(いしぐろのしょう)」という後三条天皇ゆかりの荘園が広がり、そこを拠点とした豪族の石黒氏が福光城を構えたといわれる。
『源平盛衰記(げんぺいせいすいき)』などによれば寿永2年(1183)、源平が争った俱利伽羅合戦に際し、福光城に在城していたとされる石黒太郎光弘らが木曽義仲軍に味方し、勝利を収めている。福光城の規模は、堀も含め東西27間、南北16間ほどであった。文明13年(1481)、石黒氏が井波瑞泉寺の一向宗勢力との争いに敗れ、福光城は荒廃の一途をたどった。
寛政期(1789~1801)末に福光の豪商が城跡に小亭を建て、これが後に「栖霞園」と呼ばれ、句会や寄合の場などとして利用されていた。その後、荒廃と再興を繰り返し、慶応年間(1865~1868)に加賀の茶人・桑原宗宜(くわはらそうぎ)の監修で建替えられ、今の茶室の様式になった。
後年に、福光ゆかりの松村謙三(まつむらけんぞう)、棟方志功が訪れた他、正岡子規門下の詩人、高浜虚子が栖霞園にて詠んだ句の石碑が敷地内に残されている。