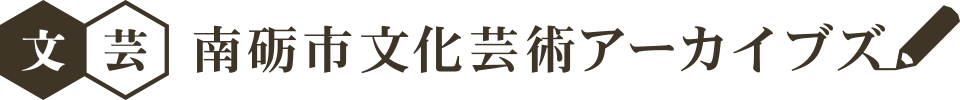城端千代音加礼
- 城端
- 市指定
- 無形民俗文化財


概要
| 名称 | 城端千代音加礼 じょうはなちょんがれ |
|---|---|
| 地域 | 城端 |
| 指定 | 市指定文化財 |
| 種類 | 民俗文化財 無形民俗文化財 |
| 所在地 | 南砺市城端 |
| 指定年月日 | 平成15年6月4日 |
| 所有者 | 城端千代音加礼保存会 |
解説
毎年9月2日に城端別院善徳寺で「一心講(いっしんこう)」と呼ばれる行事が催され、一心講踊り(盆踊り)が奉納されている。唄や囃子を加えた踊りは「千代音加礼」と呼ばれ、唄は仏教の法話が含まれている『目連尊者(もくれんそんじゃ)』や、民話から伝わったと考えられる『俵藤太(たわらとうた)縄ケ池伝説物語』が唄われる。
一心講踊りは、鎌倉時代の時宗の布教に使われた踊り念仏の影響や、文明3年(1471)の本願寺八代蓮如による浄土真宗の北陸進出の際に民衆への布教の手段として各地に広まり、江戸時代初期には存在していたと考えられる。
千代音加礼については、江戸時代中期頃に願人坊主(がんにんぼうず)といった大道芸人が世相風刺を含んだ節を語る阿呆陀羅経に近いものと思われる。
城端千代音加礼の特徴は踊り始めの『末さか』、踊りの輪を作ってから始める『目連尊者』、終盤は辛口(からくち)(踊りを止めて休んでいる間に唄うつなぎの事)『けいけいづくし』などを唄う点である。